生前贈与で賢く節税|贈与税の基礎知識と活用法をわかりやすく解説
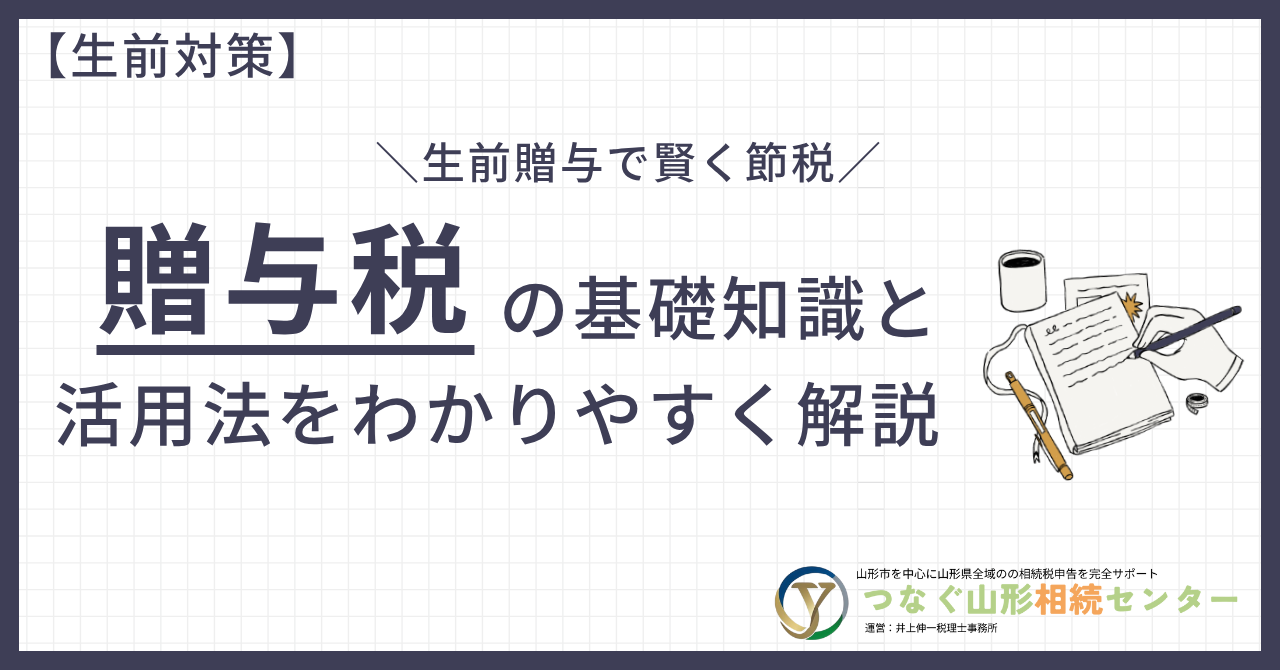
はじめに:元気な今だからできる、未来への最高の贈り物
ご自身が元気なうちに、大切な財産を愛するお子様やお孫様へ託したい…。
そして、将来ご家族が支払うことになるかもしれない相続税の負担を、少しでも軽くしてあげたい…。
『生前贈与』を考え始めるそのお気持ちは、ご家族への深い愛情と配慮の表れでございます。
生前贈与は、計画的に正しく行うことで、将来の相続税を大きく節税できる、非常に有効な手段です。しかし、その一方で、やり方を間違えると、かえって高額な「贈与税」がかかってしまう可能性も秘めています。
この記事では、「贈与税」の基本的なルールから、賢く節税するための具体的な活用法、そして失敗しないための重要な注意点まで、専門家が丁寧に解説してまいります。
1. そもそも、なぜ生前贈与で節税できるの?
相続税は、亡くなられた方が遺した財産の総額に対して課税されます。
つまり、亡くなった時点での財産が少なければ、相続税も少なくなる、というのが基本的な考え方です。
生前贈与とは、ご自身が元気なうちに、将来相続人となる方へ少しずつ財産を移しておくことで、亡くなった時に遺る財産の総額そのものを減らしておく、という相続税対策なのです。
「大きな器の水を、小さなコップで、時間をかけて少しずつ汲み出しておく」ようなイメージを持っていただくと分かりやすいかもしれません。
2. 贈与税の基本ルール「110万円の非課税枠」を知ろう
生前贈与を考える上で、絶対に知っておかなければならないのが「贈与税」のルールです。
贈与税には、「暦年課税(れきねんかぜい)」という制度があり、ここに大きな非課税枠が設けられています。
【黄金ルール】
財産をもらう側(受贈者)一人につき、毎年1月1日~12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円までであれば、贈与税は一切かからず、申告も不要です。
この「年間110万円」という非課税枠を、いかに上手に活用するかが、生前贈与による節税の最大のカギとなります。
3. 110万円の非課税枠、賢い3つの活用法
活用法①:長期間・複数人へ、毎年コツコツ贈与する
最も基本的で、かつ効果の高い方法です。
例えば、お子様2人、お孫様2人の合計4人へ、毎年110万円ずつ贈与を続けた場合を考えてみましょう。
【計算例】
110万円 × 4人 × 10年間 = 4,400万円
10年間続けるだけで、実に4,400万円もの財産を、一切税金をかけずに次の世代へ移転させることができます。早くから始めることが、この方法の効果を最大化するポイントです。
活用法②:「あげたつもり」はNG!必ず証拠を残す
税務署に「これは正式な贈与です」と認めてもらうためには、客観的な証拠を残すことが極めて重要です。
- 贈与契約書を作成する:「いつ、誰が、誰に、いくら贈与したか」を記した簡単な契約書を毎年作成し、贈与者と受贈者の双方が署名・押印しましょう。
- 銀行振込で行う:手渡しではなく、銀行振込で贈与することで、お金の流れが通帳に明確に記録されます。
- もらった人が口座を管理する:お子様やお孫様名義の口座へ振り込んでも、その通帳や印鑑を贈与した側が管理していると、「名義預金(故人の財産)」とみなされ、贈与が否認されてしまいます。必ず、もらった本人が自由に使える状態で管理することが必要です。
活用法③:孫への贈与で、世代を飛び越える
お子様だけでなく、お孫様への贈与も非常に有効です。本来であれば「親→子」「子→孫」と2回かかるはずの相続税を、1回スキップできるため、長期的に見ると大きな節税効果が期待できます。
4. 失敗しないための3つの重要注意点
注意点①:相続開始前「3~7年以内」の贈与は、相続財産に加算される
これが最大の注意点です。相続税対策として贈与を行っても、亡くなられた日から遡って3年以内に、相続人(子など)へ行った贈与は、なかったことにされ、相続財産の総額に足し戻されてしまいます(生前贈与加算)。
さらに、2024年からの税制改正で、この期間が段階的に「7年」まで延長されることになりました。
このルールがあるため、相続税対策は、より一層、元気なうちから計画的に、そして早めに始めることが重要になります。
注意点②:「定期贈与」とみなされるリスク
毎年、同じ日に、同じ金額を、契約書も交わさずに贈与し続けると、税務署から「1,100万円を10年間に分割して贈与することを、最初から約束していた(定期贈与)」とみなされ、贈与総額1,100万円に対して、一度に高額な贈与税が課せられる危険性があります。
これを避けるためにも、贈与契約書は毎年作成し、贈与の時期や金額を少しずつ変えるといった工夫も有効です。
注意点③:不動産や株式の贈与は、別の税金に注意
贈与する財産が現金ではなく不動産の場合、贈与税とは別に「不動産取得税」や「登録免許税」がかかります。これらの税金は、相続で取得した場合よりも税率が高くなるため、慎重な判断が必要です。
まとめ:元気な今だからこそできる、最高の「未来への贈り物」
生前贈与は、正しく、そして計画的に行うことで、ご家族の未来の負担を大きく減らすことのできる、素晴らしい愛情表現の一つです。
しかし、そのルールは年々複雑化しており、特に近年の税制改正を考慮すると、専門家の知識なしに進めるのは、かえってリスクが高いとも言えます。
どの制度を、いつ、誰に、いくら使うのが最適か。それは、皆様の財産状況やご家族構成によって、答えが全く異なります。
私たち「つなぐ山形相続センター」は、目先の節税だけでなく、皆様のご家族の10年後、20年後を見据えた、長期的な視点での生前贈与・相続対策プランをご提案いたします。
元気な今だからこそできる、最高の「未来への贈り物」を、私たちと一緒に準備しませんか。
どうぞお気軽に、私たちの無料相談をご利用ください。




コメント