預貯金の相続手続き|銀行での解約・名義変更に必要な書類とスムーズな進め方
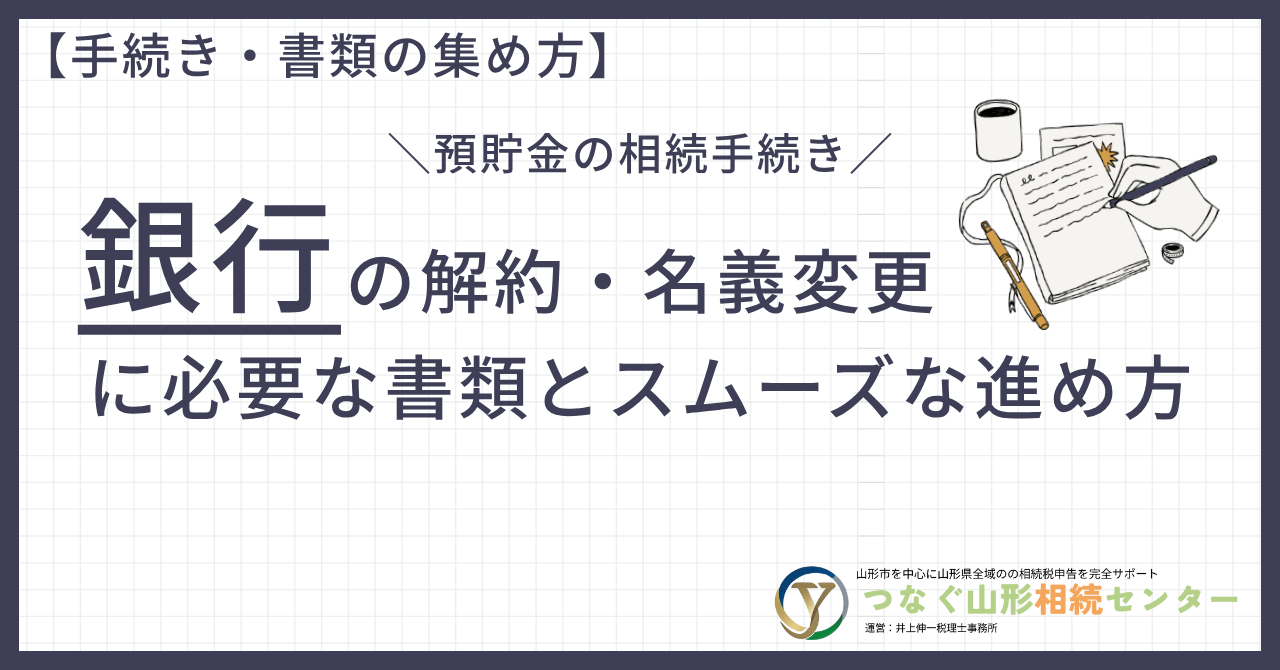
はじめに:故人の預金通帳を手に、どうすれば…とお困りではありませんか?
大切なご家族が遺された預金通帳。
「このお金は、どうやって引き出せばいいのだろう?」
「手続きには、どんな書類が必要で、どれくらい時間がかかるの?」
金融機関での手続きと聞くと、なんだか複雑で難しそうに感じられ、一歩を踏み出すのにご不安を感じていらっしゃるかもしれませんね。
ご安心ください。預貯金の相続手続きは、必要な書類と流れさえ事前に把握しておけば、決して難しいものではございません。
この記事では、金融機関での預貯金の相続手続きの基本的な流れから、ケース別に必要となる書類の完全チェックリスト、そして手続きを少しでもスムーズに進めるためのコツまで、専門家が丁寧に解説いたします。
まず知っておくべきこと:その口座は「凍結」されます
ご家族が亡くなられたことを金融機関が知ったその瞬間から、故人様名義の預貯金口座は「凍結」されます。
「凍結」とは、その口座からの一切の入出金(引き出し、預け入れ、自動引き落としなど)ができなくなる状態を指します。
「なぜ、そんなことを?」と驚かれるかもしれませんが、これは金融機関が故人の大切な財産を守るための、非常に重要な措置なのです。
相続人が複数いる場合に、誰か一人が勝手にお金を引き出してしまい、後のトラブルに発展することを防ぐ目的がございます。
この「凍結」を解除し、預貯金を相続人の皆様が受け取るための正式な手続きが、これからご説明する「相続手続き」でございます。
預貯金相続の基本的な流れ 4ステップ
金融機関によって細かな違いはありますが、手続きの大きな流れは以下の4ステップです。
ステップ1:金融機関へ連絡し、相続手続きを申し出る
まず、故人が口座を持っていた金融機関の支店窓口へ連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。
すると、その後の手続きに必要な書類一式(相続届など、金融機関所定の用紙)をもらうことができます。
ステップ2:必要書類を収集する
金融機関から指示された必要書類を集めます。
この書類集めが、相続手続きの中で最も時間と手間がかかる部分です。どのような書類が必要になるかは、次のセクションで詳しく解説いたします。
ステップ3:書類を金融機関の窓口へ提出する
収集した書類と、金融機関の用紙に必要事項を記入・押印したものを、窓口へ提出します。
書類に不備がなければ、金融機関での審査が始まります。
ステップ4:解約・払い戻しの手続き実行
書類提出後、通常2週間~1ヶ月程度で手続きが完了します。完了すると、指定した相続人の代表者口座へ、預貯金が利息と共に振り込まれるか、現金で払い戻されます。
【完全チェックリスト】相続手続きに必要な書類一覧
必要書類は、「遺言書の有無」や「遺産分割協議書の有無」によって異なります。ご自身の状況に合ったケースをご確認ください。
ケースA:遺産分割協議書に基づいて手続きする場合(最も一般的なケース)
| 必要書類 | 備考 |
| 金融機関所定の相続届 | 相続人全員の署名・実印の押印が必要です。 |
| 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等 | 連続した全ての戸籍・除籍・改製原戸籍が必要です。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行後3ヶ月または6ヶ月以内のもの。 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の実印が押印された原本。 |
| 代表で預金を受け取る方の実印と印鑑証明書 | |
| 代表で預金を受け取る方の本人確認書類 | 運転免許証やマイナンバーカードなど。 |
| 亡くなった方の通帳・キャッシュカードなど | 紛失していても手続きは可能ですが、あった方がスムーズです。 |
ケースB:遺言書に基づいて手続きする場合
| 必要書類 | 備考 |
| 金融機関所定の相続届 | 遺言執行者または受遺者の署名・実印が必要です。 |
| 遺言書(原本) | 公正証書遺言以外の場合、家庭裁判所の「検認済証明書」も必要です。 |
| 亡くなった方の死亡が確認できる戸籍謄本 | |
| 預金を受け取る方(受遺者)の印鑑証明書 | |
| 遺言執行者がいる場合は、その方の印鑑証明書 | |
| 亡くなった方の通帳・キャッシュカードなど |
※ご注意
上記はあくまで一般的なリストです。金融機関ごとに独自のルールや書式があるため、必ず事前に手続き先の金融機関にご確認ください。
手続きをスムーズに進めるための3つのコツ
コツ①:相続人の代表者を一人決めておく
金融機関との主な連絡窓口や、最終的にお金を受け取る代表者を一人決めておくと、手続きが非常にスムーズに進みます。全員がバラバラに金融機関へ問い合わせると、話が混乱する原因になります。
コツ②:最初に「残高証明書」の取得を申し出る
遺産分割協議や相続税の申告には、故人が亡くなった日(相続開始日)時点での預金残高を証明する「残高証明書」が必要です。
金融機関へ最初の連絡をする際に、この残高証明書の発行も一緒に依頼しておくと、二度手間を防げます。
コツ③:複数の金融機関の手続きは”並行して”進める
故人が複数の金融機関に口座を持っていた場合、一箇所ずつ順番に手続きをする必要はありません。
必要書類である戸籍謄本一式は、どの金融機関でも共通です。
原本還付を依頼したり、法定相続情報一覧図を活用したりすることで、同時に複数の金融機関の手続きを進めることが可能です。
まとめ:煩雑な金融機関の手続きは、専門家が代行いたします
預貯金の相続手続きは、一つひとつの作業は単純ですが、戸籍謄本の収集や、複数の金融機関とのやり取りなど、時間と労力がかかるのが実情です。
「平日に何度も銀行へ行く時間がない」
「たくさんの書類を集めるのが、とにかく大変…」
そう感じられたら、どうぞお気軽に私たち「つなぐ山形相続センター」にご相談ください。
私たちが皆様の代理人として、戸籍の収集から各金融機関とのやり取り、書類の作成・提出まで、預貯金の相続手続きの全てを代行いたします。
皆様は、ご自宅にいながらにして、手続きの完了を待つだけです。
初回のご相談は無料で承っております。まずはお話をお聞かせいただくことから、皆様のご負担を軽くするお手伝いをさせていただければ幸いです。




コメント